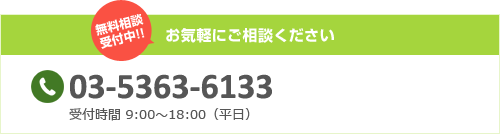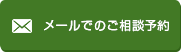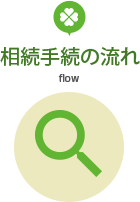HOME
HOME- >
- 相続放棄
相続財産の中に、マイナスの財産が明らかに多い場合等、相続することを望まない場合には、相続放棄という手続を行うことができます。
相続放棄をするためには、原則として、(1)相続の開始があったこと、(2)自分が相続人であることの2つを知ったときから、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続を行うことが必要です。

![]()
相続財産の調査(プラスの財産・マイナスの財産)
◆相続財産の調査のお手伝いをいたします。
![]()
![]()
相続への対応(相続放棄をすること)の決定
![]()
![]()
戸籍等の必要書類の収集
◆戸籍等の必要書類の収集を代行します。
![]()
![]()
家庭裁判所への申述手続
◆申述書を作成いたします。
![]()
![]()
家庭裁判所からの照会書の送付→必要事項を記入して返送
◆照会書の記入方法等で分からない点がございましたら、ご案内いたします。
※事案によっては、照会書の郵送でのやり取りではなく、家庭裁判所に出頭して裁判所からの質問に回答する審問手続を求められることもあるようです。
![]()
![]()
相続放棄申述手続の完了
◆家庭裁判所で審理され、問題なく受理されますと相続放棄の申述手続は完了です。
◆家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
![]()
![]()
その後の対応(債権者等への通知)
ご要望がございましたら、「相続放棄申述受理証明書」の取得・債権者への通知をサポートします。
- 1.原則として、相続の開始と自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述手続をすることが必要です。
- 2.相続放棄の申述をし受理されてしまうと、相続放棄の撤回をすることはできません。
- 3.相続放棄をした場合は、プラスの財産も一切相続することはできません。
- 4.相続放棄の申述手続前に、相続財産を処分したり消費したりしてしまっている場合には、相続放棄の申述が受理されず、相続放棄できない(マイナスの財産も相続しなければならない)可能性が高くなります。
- 5.相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とはならなかったものとみなされます。他に同順位の相続人がいればその方の相続分が増加し、該当者がいない場合には次の順位の相続人に相続権が生じます。
| 相続放棄手続サポート | 報酬4万円 ※必要な戸籍等の取得実費が別にかかります。 |
|---|
※3か月を経過してしまっている場合にはご相談ください。
※お手元にある場合にはご用意いただけますと、ご相談がスムーズに進みます。もちろん、お手元になくご用意が難しい場合でも、もちろんご相談可能です。
(1)取得済みの住民票や戸籍等(取得済みのものがある場合で結構です。)
(2)借入金等がある場合には、借入先や借入金額等が分かる書類